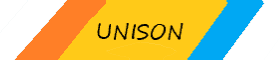【クラリネット】音程が低くなる原因
みなさんこんにちは。寒い季節はとにかく音程が下がります。みなさんは音程が下がる原因をご存知でしょうか。
音の速さ
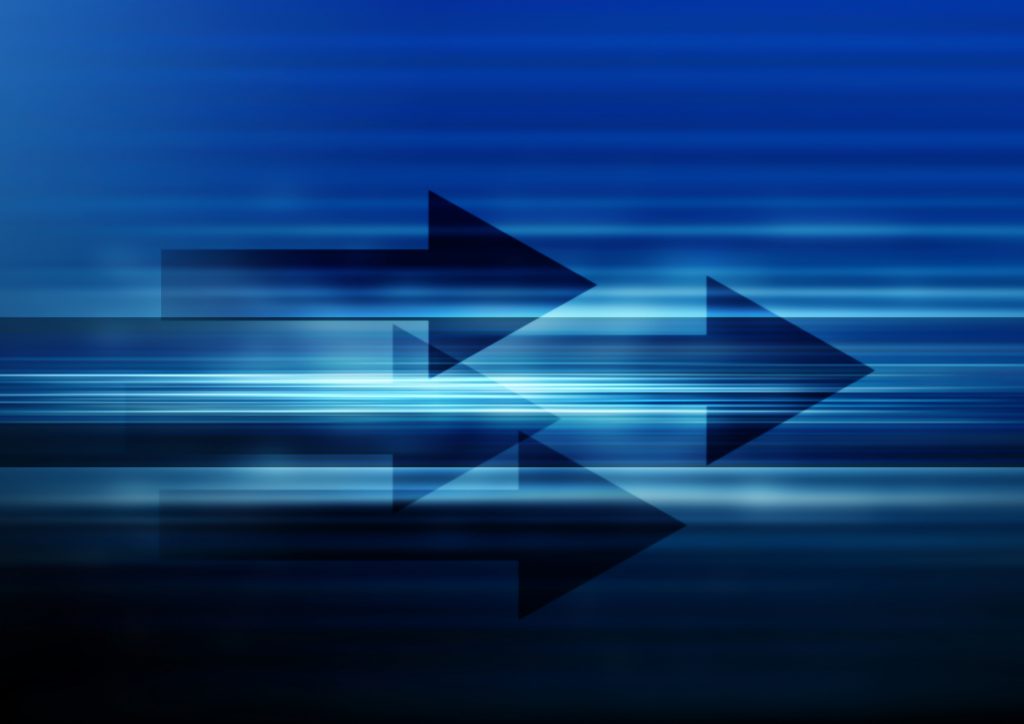
クラリネットだけに限らず、管楽器は気温によってピッチが変わります。気温によって、ピッチが高かったり低かったりするのは、音の伝わる速さが温度によって違うからです。
「音」とは振動です。空気や水、金属などいろいろなものを介して耳に届きます。
振動は、周りの空気を押し出します。押し出された空気が圧縮され、空気が濃くなります。そして、隣の空気を押し出します。これにより順々に空気の濃い部分と薄い部分ができます。この空気の圧力の変化が波となって伝わります。これを「音波」と言います。
音の速さは、気温が0度の場合一秒間に約331m進みます。この気温が1度上がるにつれて0.6m速くなります。
音の高さは、一秒間に空気の振動する回数です。振動数が多いほど高く、振動数が少なければ低くなります。
ここで温度による管体の伸び縮みを無視して、長さが変化しないと仮定します。気温が下がると、音速が遅くなります。管体の長さが変化しない(波長は同じ)ので、振動数が下がります。振動数が少なくなるということは、ピッチが下がるということです。
対策!
ここで、音程が下がって周りと合わせられないという方に、簡単にできる対策をご紹介します。(詳しい音程の取り方はこちら→正しい音程の取り方・合わせ方)
- 楽器をきちんと温めた状態で演奏する。
部屋の温度をしっかりあげて、楽器を温めてから演奏しましょう。楽器が冷えた状態だと、低くて音程が合いません。それに冷えた状態でいきなり演奏すると管体の割れの原因にもなります。 - 樽(バレル)を変える
バレルを変えるのも一つの手段です。大体付属のバレルの長さは65mm・66mmなので、短いバレルに変えることで、音程を高くすることができます。様々なメーカーから出ているので、好みの音色、音程で演奏できるものを探してみましょう。 - 周りに合わせてもらう
普段チューニングするとき442Hzで合わせると思います。どうしてもこのピッチで合わせることが難しかったら、一緒に演奏している人に441Hz、440Hzのピッチに合わせてチューニングしてもらいましょう。そうすることで、無理にピッチをあげなくても、全体のピッチが下がることで、音程が合いやすくなります。
ですが、少人数のアンサンブルなら大丈夫ですが、吹奏楽やオーケストラなど、大きな編成のだと、他の楽器のこともありできないことがあるので注意しましょう。
まとめ
演奏する環境によって、気温は違います。気温によってピッチが上がったり下がったりすることを理解して、どんな状況になっても演奏できるような対策が必要になります。ですが、どんな対策をとっても音程を合わせるには音をよく聴くことが大切です。物だけに限らず、自分の耳でよく聴いて、合わせるように意識しましょう。